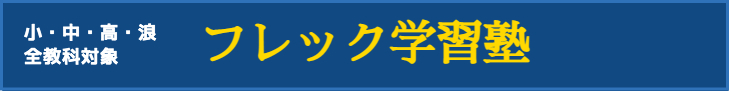千石教室の南です。
新学年の生活にも慣れてきたでしょうか?
学年が変わり、新しい分野の勉強が難しく戸惑っている人も多いのではないでしょうか?
あっという間に定期テストですから、頑張って授業について行ってください。
最近、中学英語のto不定詞 の章の質問をよく受けます。
最近の中学では、文法の授業をほぼやっていないせいか、全く意味がわからずに、「文脈」で訳している人がかなり増えてきたという感覚があります。
「文脈」というと聞こえがいいですが、結局、「勘」で訳しているにすぎません。
これでは高校受験は乗り越えられても、その後でつまづいてしまいます。
なぜなら、大学受験の文章は、抽象的で難解なため、そもそも文脈が取れないからです。
意味のわからない文章を訳さなきゃいけないのに、to不定詞の意味まで文脈で推測しようと思っても、その文脈がわからない、そもそも何についての文章かさえわからないので、無理ゲーなんです。
不定詞には有名な
・名詞的用法
・副詞的用法
・形容詞的用法がありますよね。
で、入試問題では
「これは何用法ですか?」という問題がでることはないわけです。
しかし、英語ができる人で、この用法のつかいわけができない日本人は私は見たことがありません。
なぜか?
例えばI have a pen.という文章なら小学生でもわかる文章ですよね?
しかしこれが、
I have a pen to write with.
というふうに、英語というのはは文章が長くなるとわかりにくくなります。
文章が長くなる理由は、
ある単語を補うために新たな文章をくっつけるからです。
今回の例でいうと、ただの「ペン」ではなく、「私が手紙を書くための」「ペン」と詳しく説明するから長くなるわけですね。
英語はそういう、
「どの部分が、どの単語を修飾しているか。」
言い換えれば
「どの節が、どの単語にかかっているか。」を読み解く必要があります。
で、不定詞は、関係代名詞の前段階として、「かかっている」場所を探すいい訓練になるわけです。
つまり、不定詞ができない人は、かなりの確率で関係代名詞もできないことになります。
ですから、まずは不定詞の用法の判別を理解するようにしましょう。
逃げていると、文章が難しい問題の時に苦労しますし、大学受験の時にはもう取り返しがつかないことになっていますよ。